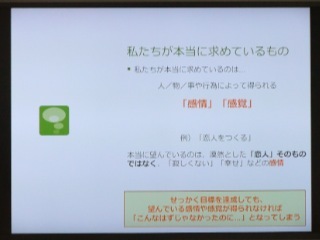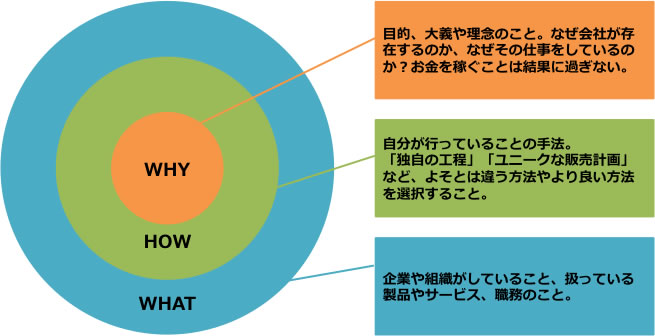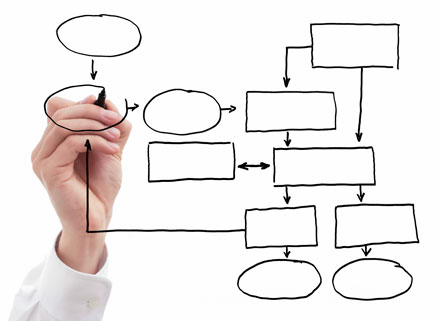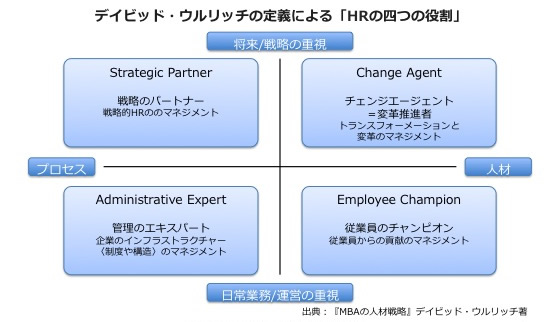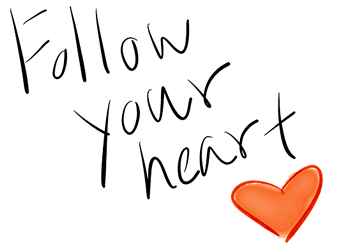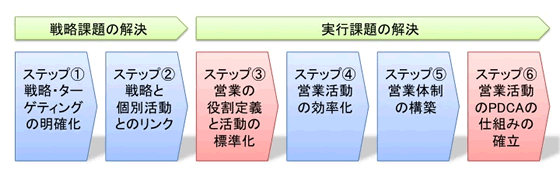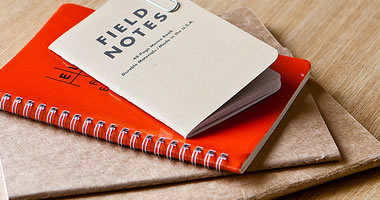| 本は絶対、1人で読むな! | |
 |
中島 孝志
潮出版社 2010-11 |
勉強会や読書会がブームだと言われていますね。私も最近「プレゼン読書会」を始めましたが、最も工夫が必要なのが、「いかに参加者に効果を感じてもらうか」というところです。暇つぶしでやるなら問題ないかもしれませんが、そうでなく本気で勉強したい人は必ず「時間」と「効果」を天秤にかけるはずです。
いくら読書会を開いても、「私はこの本を読んでこうを感じました。」「へー、そうなんだ。でもオレにはあんまり興味がないな。」程度のやりとりで終わってしまうのであれば、集まることのメリットが感じられず、だったら一人で本を読んでたほうがましだなと思われてしまいます。じゃあ共通のテーマを決めて、課題図書を読んでくればいいじゃないかとなりますが、今度は課題図書をどう決めるのかという問題が出てきます。1日に何冊も読める人であれば構わないかもしれませんが、週に1冊とか、月に1冊のペースで読書をしている人には、自分の好きなテーマの本を読めないという不満が出てしまいます。
やってみるとなかなか読書会は難しいものです。そこで今日は中島孝志さんの『本は絶対、1人で読むな!』を読んでみました。その中から読書会を軌道にのせるためのヒントになりそうなポイントを7つ紹介します。
1.参加者同士のディスカッションを促す
わざわざ時間を作って皆であつまる目的は何でしょうか。本を読むこと?違いますよね。本は一人でも読めますが、他の人にその内容を共有したり、そこから先のディスカッションを通してメンバーと関連情報や裏話、異なる視点や意見を交換し、さらに深く考える機会を得られることこそが、皆で集まる利点なのです。本はあくまで話のネタくらいのつもりで、読んだ本の紹介で終わるのでなく、参加者同士でフィードバックしあえる仕組みを作りましょう。
2.質問を促す
自分ではわかったつもりになっていたことでも、人に話してみてツッコまれ、実はよくわかっていなかったなんていうことはよくあります。読書会でも一緒で、本から得られた情報を自分なりに解釈・加工した上で相手に話してみれば、論理の飛躍や要素の欠如に気づくことができます。皆が分かっているようで実はわかっていない、そんな質問がもらえることも読書会の醍醐味です。どんどん質問することを奨励しましょう。
3.テーマを縛らない
私が最近はじめた「プレゼン読書会」ではあえてテーマを絞らず、各自自由にネタを用意してもらうようにしました。そのかわり「単なる自己満足の発表」にせず、他のメンバーに対して「こういう風にしてみてはどうでしょうか?」という提案の形にして事前に発表内容を用意してもらっています。先日第一回目を開いた際に「テーマがバラバラだと、逆にみんながどういう事に問題意識を持っているのかがわかって面白いね!」という意見が出たのですが、まさにそのとおりなのです。
人は同じ情報を見たり、景色を見たりしても、自分が意識していることしか目に入らないし、頭に残りません。本でも同じで、持っている問題意識によって本を選ぶ際の視点や内容の捉え方が様々なのです。自分自身では見落としてしまうテーマにこそ実はヒントがあったなんていうことはよくあるので、読書会でもそういううれしい偶然を取り入れるようにしましょう。
4.定期開催を守る
読書会のモチベーションを大きく下げてしまうのが、直前の欠席や、サボりをする人たちです。このような事態を防止するためにも、読書会を開催するなら定期的、継続的に開催するようにしましょう。「毎月第何何曜日」という風に開催日を定例化してしまい、「この日は読書会だから予定は入れられないな」とメンバーの頭にインプットすることが出来れば、サボリや欠席も減り、長続きします。
5.思い切って一部屋借りてしまう
読書会をする上で問題となることの一つが、場所をどうするかです。定番はカフェですが、席を確保しにくかったり、周りの人に気を使わなければならなかったりと、いまいち居心地が良くありません。プレゼン読書会はうちのリビングで開催してますが、10人くらいの人数なら十分座れるスペースがありますし、46型テレビに資料を映すこともできるので、カフェよりも勉強がはかどります。
自宅が無理なら、いっそ部屋を借りてしまうのも手です。メンバーで割り勘すれば月々5000円程度ですみますし、隠れ家的な要素があり勉強会へのモチベーションも上がることでしょう。
6.ブログで宣伝する
せっかく読書会を開くなら、いろんな人に参加してもらいたいものです。そのためにも是非ブログで読書会の告知をしましょう。会の趣旨や開催レポート、参加者の告知などを載せておけば、興味を持った人が参加を希望してくれるかもしれません。プレゼン読書会でも、各自のプレゼン内容を簡潔にまとめて掲載してみようと思います。また、読書会に興味がある方は歓迎なので、是非声をかけてくださいね。
7.発表内容を録音する
最近は本の内容を音声で聞きたいという要望も多いそうですし、読書会でのディスカッションの内容を録音し、ブログにアップロードして配信するのも有効かもしれません。プレゼン読書会では今のところアップロードまでは考えていませんが、各自があとで自分のプレゼンテーションを聞いてみることで、話しているときには気付けない自分の癖などを知ることができ、面白いのではないかと思いました。これも早速取り入れたいと思います。
【まとめ】
著者自身が書評ブログや読書会、勉強会の開催で実績を持たれているので、特に読書会を開催しようと思っている人にはヒントが満載の一冊です。せっかく読書をしているのですから、学びを一人で終わらせず、読書会を開いてドライブをかけてみましょう!
| 本は絶対、1人で読むな! | |
 |
中島 孝志
潮出版社 2010-11 |
 ホーム
ホーム 管理人について
管理人について ブログ記事
ブログ記事 スティーブ・ジョブズ
スティーブ・ジョブズ 業務改革/BPR
業務改革/BPR IT/ツール
IT/ツール ビジネススキル
ビジネススキル 読書/勉強法
読書/勉強法 ワークスタイル
ワークスタイル 管理人の日記
管理人の日記 雑学ネタ
雑学ネタ コンタクト
コンタクト







![影響力の武器[第二版]―なぜ、人は動かされるのか](http://images.amazon.com/images/P/4414304164.09._SCTHUMBZZZ_.jpg)